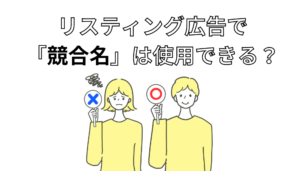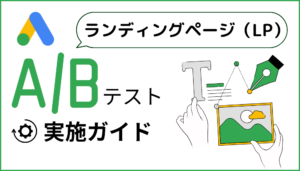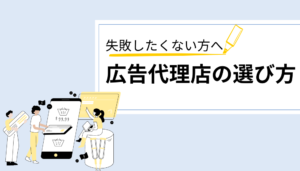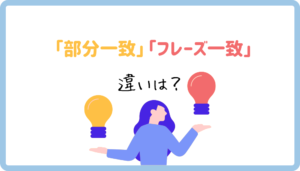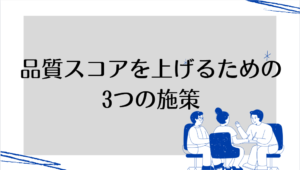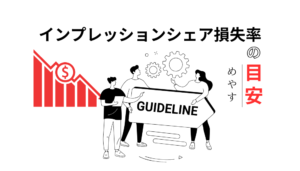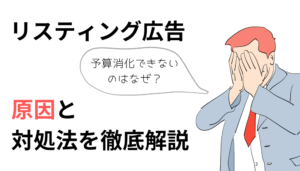広告運用はインハウス化すべき?代理店活用との比較・よくある失敗例を解説

「そろそろ広告運用を社内で回したい」
「コスト削減のために、代理店への依存を減らしたい」
そんな思いから、インハウス運用を検討する企業が増えています。
しかし、実際にインハウス化を進めてみると、
「成果が出ない」「人材が育たない」「思ったより工数がかかる」といった、新たな悩みに直面するケースも少なくありません。
インハウス化には確かに、コスト削減やスピード向上といった大きなメリットがあります。
一方で、リソース・スキル・体制が不十分なまま進めると、かえって広告効果が落ちてしまうリスクもあるのです。
「うちの会社にインハウス運用は向いているのか?」
「失敗せずに内製化するには、何から始めればいいのか?」
そんな疑問を解消できる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
インハウス運用とは?
インハウス運用とは、広告運用を自社内で完結する体制のことを指します。
外部の広告代理店に委託せず、社内の担当者が広告の企画、制作、運用、分析まで一貫して行うスタイルです。
近年、デジタル広告の重要性が高まる中で、「スピード感をもって運用したい」「広告の成果をより自社の戦略に直結させたい」と考える企業が増え、インハウス化に注目が集まっています。
インハウス化を進めることで、広告に関する意思決定の自由度が高まり、コスト削減やナレッジ蓄積といったメリットが期待できます。
一方で、社内に広告運用の専門知識を持つ人材や体制が求められるため、準備不足のまま進めるとリスクも伴う取り組みと言えるでしょう。
インハウス支援型広告代理店とは?
インハウス支援型広告代理店とは、企業の広告運用をすべて代行するのではなく、
自社内での運用(インハウス運用)を目指す企業に向けて、運用ノウハウの提供や立ち上げ支援、改善サポートを行うパートナー企業のことを指します。
単なる「運用代行業者」ではなく、
- 社内運用体制の立ち上げ支援
- 運用担当者へのノウハウ移転
- 改善サイクルの定着サポート
などを通じて、クライアント企業が自走できる運用力を育てる役割を担っています。
インハウス支援型代理店を活用することで、
初期段階からいきなりすべてを自力で構築する負担を減らし、よりスムーズに、かつ効果的にインハウス化を進めることが可能になります。
次章では、外部の広告代理店との違いや、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく見ていきます。
インハウスと外部代理店の違い
広告運用を進める際、インハウス運用と外部広告代理店の活用では、体制や費用、柔軟性に大きな違いがあります。
それぞれの特徴を理解し、自社に合った運用スタイルを選ぶことが重要です。
運用体制・コスト・柔軟性の比較
| 比較項目 | インハウス運用 | 外部広告代理店 |
|---|---|---|
| 運用体制 | ◎(社内で完結。コントロール性が高い) | ◯(外部に任せられるが、自由度は低め) |
| コスト | ◎(マージン不要でコスト削減しやすい) | △(マージン発生。ただしリソース活用可能) |
| 柔軟性 | ◎(施策変更や予算調整が即時対応可能) | △(提案・承認フローが必要でスピード感に劣る) |
| 専門性 | △(社内人材のスキルに依存) | ◎(各分野のプロフェッショナルが対応) |
| リソース確保 | △(人材確保・育成が必要) | ◎(リソースを柔軟に追加できる) |
【運用体制】
インハウス運用では、自社内に広告担当者を配置し、すべての運用業務を社内で管理します。
一方、外部代理店の場合は、戦略設計から運用実務までを外部パートナーに委託する形になります。
社内リソースの負荷は増えるものの、細かなコントロールが可能になるのがインハウスの特徴です。
【コスト】
インハウス運用は、代理店マージン(手数料)が不要なため、純粋な広告費以外の支出を抑えられます。
ただし、運用担当者の人件費やツール導入コストは別途発生します。
代理店運用はマージンが発生する一方、最新のノウハウや多媒体にまたがる運用リソースを活用できるメリットがあります。
【柔軟性】
インハウス運用は、施策変更や予算調整などの意思決定を社内で完結できるため、スピード感を持った対応が可能です。
外部代理店を利用する場合、施策の提案・承認フローが発生するため、タイムラグが生じることもあります。
どちらが向いているかを判断するポイント
インハウス運用と外部代理店運用の違いがわかったところで、次に「自社にはどちらが向いているのか」を考えてみましょう。
以下に、判断の目安をまとめます。
インハウス運用が向いているケース
- スピード感を重視し、施策を柔軟に変更したい
- 社内に広告運用経験者、またはマーケティング人材がいる
- 広告運用ノウハウを自社資産として蓄積したい
- 年間広告費が一定以上あり、マージンコストを削減したい
外部広告代理店が向いているケース
- 社内に広告運用に必要なリソースや専門知識がない
- 複数媒体を横断した大規模な広告運用が必要
- 広告運用のスキルアップより成果獲得を優先したい
- 新しい媒体やトレンドへのキャッチアップが難しい
インハウス化のメリット・デメリット
インハウス広告運用は、「もっとスピーディーに広告を動かしたい」「代理店コストを抑えたい」というニーズに応える一方で、
社内体制によっては思わぬ落とし穴もある取り組みです。
ここでは、インハウス化を検討する際に知っておきたい、現実的なメリットとデメリットを整理してご紹介します。
【インハウス化による主なメリット】
- 代理店手数料を気にせず、広告費を最大限活用できる
→ 「広告予算が増えないのに代理店手数料だけ取られる」という不満を解消できます。 - 施策変更のスピードが圧倒的に速くなる
→ 代理店経由でのやり取り不要。思いついた施策をすぐに実行できる体制が作れます。 - 広告施策を自社戦略に直結させやすい
→ 「うちの商品やターゲットをちゃんと理解してくれていない」と感じることがなくなります。 - 広告運用ノウハウが社内に蓄積され、担当者が育つ
→ 将来的には、運用担当者自身が「広告のプロ」になり、事業全体の推進力を高められます。 - 急な市場変化にも、自社判断で柔軟に対応できる
→ 外部調整なしで、キャンペーン停止や予算シフトなどのスピード対応が可能です。
【インハウス化に伴う主なデメリット】
- 広告運用できる人材をゼロから育てる手間とコストがかかる
→ 「そもそも何から教えればいいか分からない」という状況になりがちです。 - 担当者一人に依存し、異動や退職で運用が止まるリスクがある
→ 特定の人にしかノウハウが残らず、「あの人がいないと何もわからない」状態になる危険があります。 - 運用ツールや分析環境の整備にまとまった初期投資が必要
→ 広告アカウントだけでなく、レポーティングツールやBI連携なども考える必要が出てきます。 - 社内リソース不足で広告運用が後回しになりやすい
→ 日々の業務に追われ、広告運用に手が回らず、改善施策が停滞してしまうリスクがあります。 - 広告媒体やトレンドの変化についていくのが難しくなる
→ 新機能やアルゴリズム変更に対応できず、「気づいたら効果が下がっていた」という事態にもなりかねません。
インハウス化には確かに魅力的なメリットがありますが、社内リソースや成長環境を整えないまま進めると、かえって成果が出ないリスクもあります。
導入を検討する際には、単なるコスト削減だけでなく、「本当に社内で育て切れるか」という視点でも慎重に見極めましょう。
インハウス化する前に|成果を出せる体制が整っているか?
インハウス広告運用は、コスト削減やスピード改善といった魅力がある一方で、
体制が整っていない状態でスタートすると、かえって成果が出ないリスクも高くなります。
たとえば、広告運用経験者が社内にいなかったり、マーケティングデータを活用する仕組みが弱い場合、インハウス化しても「運用は回っているが成果が見えない」という状態に陥りがちです。
また、日々の業務に忙殺される中で広告運用が後回しになり、改善施策を打たないまま成果がジリ貧になるケースも少なくありません。
本当にインハウス化を進めるべきかを判断するうえでは、
- 広告運用を担う人材・チームが社内にいるか
- PDCAを自律的に回す文化・仕組みがあるか
- 分析結果から戦略を立て直す体制が整っているか
といった点を、冷静に見極めることが欠かせません。
できるかどうかではなく、
成果が出せるかどうかという視点で判断する──。これが、インハウス化を成功に導く第一歩です。
インハウス化の立ち上げ手順【5ステップで解説】
インハウス広告運用を成功させるためには、勢いで進めるのではなく、正しい順番で準備と実行を進めていくことが大切です。
インハウス化をスムーズに立ち上げるための流れは、次の5ステップです。
まずは現状を把握し、どこまで社内で運用できるかを見極めたうえで、必要な人材やツールを揃えていくことがインハウス化の第一歩です。
いきなり全施策を内製化するのではなく、小規模テスト運用で課題を洗い出し、体制とルールを整えながら徐々に拡大していくアプローチが現実的です。
運用の中で足りない部分があれば、必要に応じて外部支援を活用し、自社に最適なインハウス体制を作り上げていきましょう。
インハウス運用でよくある失敗例とその対策
インハウス広告運用を始めたものの、思うような成果が出ずに悩む企業も少なくありません。
ここでは、よくある失敗例とその対策をセットで紹介します。
失敗例① 属人化してブラックボックス化する
担当者個人のスキルや判断に依存しすぎると、運用の全体像が可視化できなくなり、異動・退職が発生した際に運用が止まってしまうリスクが高まります。
対策▶︎ 運用フローや設定変更履歴をドキュメント化し、チーム内で共有する体制を整えましょう。
定例ミーティングで進捗・改善内容を報告し合う仕組みを作ることも有効です。
失敗例② 効果改善施策が後回しになる
インハウス化直後は「広告配信を止めないこと」が優先されがちで、成果改善のための分析やクリエイティブ検証が後回しになるケースが多く見られます。
対策▶︎ 「成果改善」を必ずKPIに組み込み、週単位で改善活動を振り返る運用リズムを作りましょう。
最初は小さな施策でもいいので、必ず改善アクションを打つことをルール化することが重要です。
失敗例③ 広告媒体のアップデートについていけない
GoogleやMetaなど主要媒体の仕様変更に追いつけず、最適な運用手法が取り入れられないまま成果が悪化するパターンも少なくありません。
対策▶︎ 主要媒体の公式ブログやニュースを定期チェックする担当を決めておきましょう。
必要に応じて外部の専門家に短期アドバイザリー支援を依頼するのも効果的です。
失敗例④ 運用担当者の燃え尽き・離職リスク
少人数で回していると、広告運用が孤独な作業になり、担当者が疲弊してしまうケースもあります。
特に、成果プレッシャーが強い環境だと離職率が高まる傾向があります。
対策▶︎ 運用担当者には成果だけでなく、「改善アクション数」や「学びの共有」も評価対象に加えましょう。
また、ナレッジ共有会や外部勉強会への参加を奨励し、孤立感を防ぐ取り組みも効果的です。
ハイブリッド型運用とは?インハウス×外部パートナーの最適バランス
インハウス化を検討する際、忘れてはならないのが「すべてを社内で完結させる必要はない」という視点です。
成果を最大化するためには、インハウス運用と外部パートナー活用を組み合わせた「ハイブリッド型運用」という選択肢も有効です。
なぜ「完全インハウス」は難しいのか
広告運用には、日常的な施策改善だけでなく、
- 複数媒体を横断した最適化
- 新しい媒体や機能へのキャッチアップ
- 大規模キャンペーン時の一時的なリソース増強
といった、幅広いスキルと対応力が求められます。
インハウスだけでこれらを常にハイレベルにこなすのは、リソース的にも現実的にもかなり負担が大きくなります。
「インハウスにしたい」という理想にこだわりすぎるあまり、運用パフォーマンスが下がってしまっては本末転倒です。
インハウスと外部支援の役割分担の考え方
ハイブリッド型運用では、社内と外部パートナーの役割を次のように整理するとスムーズです。
【インハウス側が担うべき領域】
- 自社理解が求められる戦略設計やターゲット選定
- 予算管理、社内調整など意思決定領域
- 一部の広告運用(成果重視の主要施策など)
【外部パートナーに任せるべき領域】
- 新しい媒体や機能への迅速な対応
- 大規模キャンペーン時の運用代行や一時的なリソース補完
- データ分析やレポーティングの高度化支援
このように、インハウス化を目指しながらも、
外部のリソースを上手に取り入れていくことで、
無理なく、かつ成果につながる運用体制を作ることができます。
「全部内製しなければ失敗」ではなく、「必要なところだけ内製化する」こと。
これが、インハウス広告運用を成功させる現実的なアプローチです。
担当者に必要なスキルと育成のポイント
インハウス運用を成功させるうえで、運用担当者のスキルセットと育成方法は非常に重要な要素となります。
適切な人材を配置し、成長を支援できるかどうかが、インハウス化の成否を大きく左右します。
広告運用担当者に求められるスキルセット
インハウス運用の担当者には、単に広告を回すだけでなく、次のような総合的なスキルが求められます。
- 広告媒体の運用スキル(Google広告、Meta広告など各媒体の仕様理解と実装力)
- データ分析スキル(効果測定、数値レポートの読み解きと改善提案)
- マーケティング理解(顧客心理・カスタマージャーニーの把握)
- PDCA推進力(自ら課題を設定し、改善施策を回し続ける力)
- 社内コミュニケーション能力(営業・制作チームとの調整スキル)
現場運用だけでなく、戦略や社内連携にも関わる場面が増えるため、
幅広い視野を持って行動できるタイプが適任です。
育成のために押さえておくべきポイント
担当者を育成する際には、次のポイントを押さえておくとスムーズです。
- 初期は「運用型広告」の基礎をしっかりインプットさせる(座学+実運用のセット)
- 小さなPDCAサイクルを回す経験を積ませる(小規模案件・テスト施策を任せる)
- 成果よりも「改善アクション回数」を重視して評価する
- 外部セミナー・勉強会への参加を積極的に促す
- 定期的にフィードバックを行い、成長実感を与える
一人で「広告運用のすべて」を背負わせるのではなく、
最初は「一緒に考える」「相談できる場を作る」ことが育成の鍵になります。
インハウス化に取り組む企業にとって、担当者育成は時間がかかるチャレンジですが、
長期的には広告運用だけでなく、マーケティング全体をリードできる人材育成につながる大きな投資となります。
インハウス化にかかるリアルなコスト・期間
インハウス化を検討する際、最も気になるポイントのひとつが、
「実際にどれくらいコストや時間がかかるのか」という点ではないでしょうか。
ここでは、一般的な目安を整理してご紹介します。
初期費用にかかるコストイメージ
- 人件費
→ 運用担当者を新たに採用する場合、年収400〜600万円程度が相場です。
すでに社内人材をアサインする場合でも、育成コスト(教育時間・研修費用)が発生します。 - ツール・システム導入費
→ 運用効率化や効果測定のためのツール(広告管理、レポート作成ツールなど)に、
月額5万〜15万円程度のコストがかかるケースが一般的です。 - 社内体制整備コスト
→ナレッジ共有システムの構築、社内調整フローの整備などに一定の工数が必要です。
特別なツールを使わない場合でも、担当者リソースを割く必要が出てきます。
結果として、インハウス化初年度は
「採用・ツール整備込みでざっくり600万〜1000万円程度」を見込んでおくのが安全ラインです。
インハウス化にかかる期間の目安
インハウス体制の構築には、以下のような期間感を想定しておくと現実的です。
- 初期準備期間(採用・ツール選定・体制構築)
→ 3〜6か月程度 - 小規模テスト運用期間
→ 3か月程度(部分的な媒体やキャンペーンからテスト開始) - 本格運用体制の確立
→ さらに3〜6か月程度(運用ルール整備・ナレッジ蓄積)
最短でも半年〜1年程度をかけて、段階的に体制を整えていくイメージが必要です。
「内製化すればすぐにコスト削減できる」と考えがちですが、
実際には、立ち上げフェーズはむしろ追加投資が必要になる点を十分理解しておきましょう。
【診断コンテンツ】あなたの会社はインハウス向き?自己診断チェック
インハウス化を検討する際には、
「自社が本当にインハウス運用に向いているか」を冷静に見極めることが重要です。
まずは、以下のチェックリストで自己診断してみましょう!
| ✔︎ | 設問内容 |
|---|---|
| 広告運用経験者またはマーケティング担当者が社内にいる | |
| 広告運用にかける年間予算が一定額(例:500万円以上)ある | |
| 自社の商品・サービス理解が深く、戦略を内製化したい意欲がある | |
| 小規模でも広告運用のPDCAサイクルを回した経験がある | |
| 効果測定やレポーティングを自社で行える体制がある | |
| 媒体アップデートやマーケティングトレンドへの関心が高い | |
| 社内で改善活動を継続的に回す文化・仕組みがある |
【結果の目安】
- 5個以上当てはまる → インハウス化を本格的に検討できる段階
- 3〜4個当てはまる → 部分的なハイブリッド運用から始めるのがおすすめ
- 2個以下 → まずは外部パートナーと組みながら基盤整備を進めるのが現実的
インハウス化はあくまで「手段」であり、目的ではありません。
無理に内製化を急ぐより、自社にとって最適な運用体制を築くことが成果への近道です。
「自社に合った進め方を知りたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。弊社はWEB広告の伴走型支援を行っています。
まとめ|インハウス化の成功は”自社に合わせた設計”から
インハウス広告運用は、コスト削減やスピード向上といったメリットがある一方で、体制が整っていないと成果が出にくいリスクも抱えています。
大切なのは、単に内製化を目指すのではなく、「何を目的に、どの範囲を自社で担うか」を明確にすること。
そして、必要に応じて外部パートナーと連携しながら、無理のない体制を築いていくことです。
「インハウス化を進めるべきか迷っている」
「どこから始めればいいか分からない」
そんな場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
伴走型支援をお望みならHew One’s Wayへ
Hew One’s Wayの最大の特徴は、お客様に寄り添った伴走型の支援が可能なことです。
継続的なサポートや密なコミュニケーションを重視される方は、ぜひ一度ご相談ください。