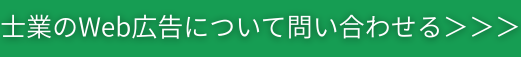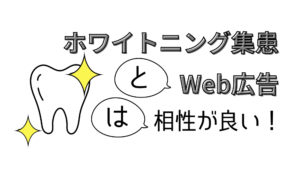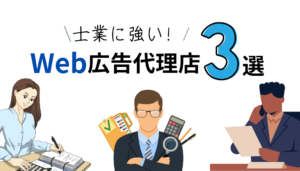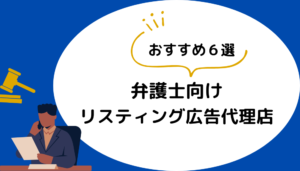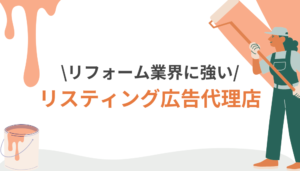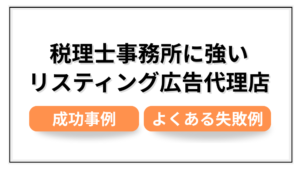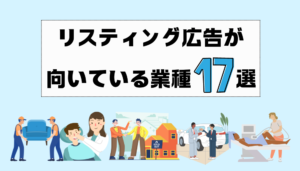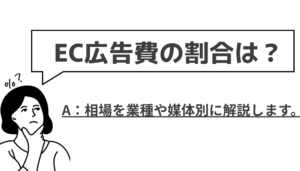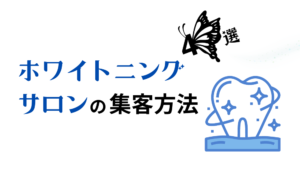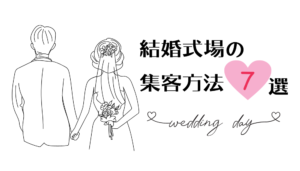士業の集客方法12選:オンラインとオフラインに分けて解説

一昔前までは、士業として事務所を構えるだけで自然と相談者が訪れることもありました。しかし現在では、「ホームページを作ったのに問い合わせが来ない」「何をすればいいのかわからない」といった声も聞かれます。
相談者の行動様式が変化し、競争も激しくなる中、待っているだけでは依頼を得られない時代です。
本記事では、士業が直面する集客の課題と、それを乗り越えるための具体策を、オンライン・オフラインの両面から解説します。
士業の集客の現状
ここ20年で士業の集客環境は大きく変化しました。かつては資格を取得し事務所を構えるだけで依頼が集まりましたが、現在ではそれだけでは集客が難しくなってきています。
背景には、以下の2つの要因があります。
・士業間の競争激化
・集客手段の多様化
まずは競争の激化から見ていきましょう。
士業間の競争激化
士業の世界では、今や「競合の激増」が避けられない現実となっています。
2000年以降、弁護士・公認会計士・税理士などの資格者数は大幅に増加しています。
| 種別 | 2000年時点 | 2023年時点 | 増加率 |
| 弁護士 | 17,126人 | 44,818人 | 261.7% |
| 公認会計士(準会員含む) | 16,656人 | 42,529人 | 255.3% |
| 税理士 | 65,144人 | 81,202人 | 124.7% |
参照元:https://learningedge.jp/column/how-to-attract-customers-for-professional-business/
一方、国内の人口は減少傾向で、相談者数は縮小しています。依頼件数が限られる中で、他士業との競合が避けられない現状においては、選ばれるための工夫と戦略がこれまで以上に求められています。
集客方法の多様化
現在では、ホームページやSNS、ウェブ広告、動画、メールなど、集客手段は多様化しています。
特に若年層をターゲットとする場合は、InstagramやYouTubeなどのSNSが効果的です。
したがって、媒体ごとに最適な手段を選定し、戦略的に活用することが重要になります。
つまり、集客方法の多様化とは単に手段が増えたということではなく、「最適な施策を選び、継続的に運用できるか」が問われているのです。
【オンライン】士業の集客方法
インターネットの普及に伴い、士業における集客手法も大きく進化しました。ここでは、オンライン施策の中で実践すべき8つの手法を紹介します。
【オンライン①】 ホームページ作成
士業のオンライン集客において、ホームページの作成は最も基本かつ重要な施策です。
ホームページは24時間365日稼働する「営業窓口」として、問い合わせ対応や業務紹介、実績提示などを通じて信頼を獲得できます。
ただし、立ち上げるだけでは不十分です。検索結果で埋もれないためにはSEO対策が必須となります。
検索キーワードの選定、構造の最適化、専門的なコンテンツの充実を図ることで、アクセスの質と量を高められます。
【オンライン②】 SEO対策
ホームページを公開した後は、“見つけてもらう”ためのSEO対策が欠かせません。
SEOとは、検索エンジンで特定キーワードを検索した際に、自社サイトを上位表示させる施策のことです。
「悩み+士業+地域(例:相続 トラブル 弁護士 東京)」などの具体的なキーワードは、ニーズのあるユーザーに届きやすく、集客に直結します。
検索者の意図を理解し、タイトルや見出し、本文に自然にキーワードを盛り込むことが成功の鍵です。
SEOは単なる技術ではなく、ユーザーの意図を正確に捉えた情報設計が求められます。
継続的な改善と発信により、ホームページの集客力を高めましょう。
【関連記事】初心者向けSEO対策のやり方:無料で使えるツールも紹介
【オンライン③】 Web広告への出稿
短期間で成果を出したい場合、Web広告への出稿が効果的です。検索エンジンやWebサイト、SNSなどで広告を配信し、見込み顧客を効率的に誘導できます。即効性に優れており、早ければ数日で反応が得られることもあります。
主なWeb広告には以下が挙げられます。
- リスティング広告:検索結果ページの上部などに表示されるテキスト型広告
- ディスプレイ広告:Webサイトやアプリ上のバナー広告
- リターゲティング広告:一度訪問したユーザーに再度広告を表示する手法
- SNS広告:XやLINEなどのタイムラインに表示
- 動画広告:YouTubeなどで動画視聴前や途中に配信される広告
- アドネットワーク広告:複数のメディアに横断的に掲載できる広告
- ネイティブ・タイアップ広告:記事型の広告で、違和感なく情報提供できる手法
- アフィリエイト広告:成果報酬型で第三者に宣伝を委託するスタイル
- 純広告:特定のWebメディアの広告枠を買い切りで掲載する形式
上記のWeb広告は、ターゲット設定が細かく行える点も強みです。たとえば、相続案件に強い司法書士は、50代以上の利用者が多いFacebook広告を活用することで、ターゲット層に効果的にアプローチできると考えられます。
また、リスティング広告の興味がある方は、こちらの記事「士業のためのリスティング広告運用ガイド|コストの抑え方も解説」もぜひお読みください。リスティング広告について深く理解りできます。
【オンライン④】 ランディングページの作成
特定サービスの集客効率を高めたいなら、ランディングページ(LP)の作成は有効です。
ランディングページとは、「債務整理」「相続税対策」など、1つのサービスに特化したWebページのことです。事務所全体を紹介するホームページと異なり、訪問者の関心に沿って申込や相談へと誘導することを目的とします。
たとえば、Web広告やSNS投稿から「相続税対策に困っている層」をLPに誘導し、無料相談へとつなげる導線設計が可能です。
LP内では、「どんな悩みを解決できるか」「その結果どうなるか」といった流れをわかりやすく伝えることが重要です。料金・対応地域・事例・プロフィールなどを整理し、信頼感を与える内容にすることで成約率は高まります。
LPは、広告やSNSからの訪問者を具体的な行動(申し込み・問い合わせ)へと導くページとして設計し、ホームページとは明確に役割を分けて活用しましょう。
【オンライン⑤】 SNSの活用
SNSの活用は、ユーザーとの接点をつくり、信頼関係を育むのに適した手段です。
士業でもSNSを活用する事例が増えており、継続的な情報発信により認知を広げるだけでなく、見込み顧客の信頼獲得にもつながります。フォローやコメント、シェアといった拡散機能を無料で利用できる点も特徴です。
たとえば、フォロワーの質問に対して専門的なアドバイスを発信すれば、「相談してみたい」と思わせるきっかけになります。
SNSでは過度な売り込みを避け、法律や税務の基本的な知識(一般の人が理解しやすい初歩的な情報)、時事ニュースの解説、Q&A形式の投稿など、“役立つ情報”の提供を心がけましょう。
即効性は低いものの、地道な発信の継続によって、将来的な相談につながる関係性を構築できるのがSNSの強みです。
【オンライン⑥】 動画の配信
動画の配信は、士業の専門性と人柄を視覚や音声を通じて伝えられる有効な手段です。
文章や画像よりも多くの情報を短時間で届けられ、視聴者の印象に残りやすいため、相談への心理的な抵抗感を和らげる効果が期待できるとされています。
たとえば、相続や債務整理などの「よくある質問」に答える形式の動画を作成すれば、同じ悩みを抱える視聴者の関心を引きやすくなります。
また、動画の最後や概要欄(動画の説明文)に事務所の情報や連絡先を掲載することで、視聴から相談への自然な導線を構築することが可能です。
動画は、ブランディング(専門家としての認知や信頼構築)と集客を兼ねたツールとして活用でき、YouTubeやInstagram、TikTokなど、目的やターゲット層に応じて発信媒体を選ぶことで効果を高めることができます。
【オンライン⑦】 メールマガジンの配信
メールマガジンは、見込み顧客との関係を継続し、相談のタイミングを逃さずアプローチできる「継続接点ツール」です。
SNSやホームページ経由でメールアドレスを取得し、登録者に定期的に情報提供を行うことで、比較検討中の見込み顧客とも接触を保てます。
たとえば、週1回や月2回のペースで、法律相談のQ&Aや時事性のある税務情報、士業の人柄が伝わるエピソードなどを盛り込むと、読者との心理的距離が縮まります。
また、メールマガジン限定の特典(例:初回無料相談や小冊子のプレゼントなど)を提供することで、申込みへのハードルを下げる効果も期待できます。
さらに、ステップメール(登録直後から複数回にわたり自動で配信する一連のメール)を活用すれば、関心の高い読者に対して段階的に情報を届けることができ、理解促進と信頼構築につながります。
【オンライン⑧】 ポータルサイトへの登録
士業ポータルサイトへの掲載は、今すぐ専門家を探している顕在層(ニーズが明確な見込み顧客)と接点を持てる、比較的手軽で費用対効果の高い集客手段です。
こうしたポータルサイトは、「弁護士を探したい」「税理士に相談したい」などの具体的な目的を持ったユーザーが訪れるため、相談意欲が高い傾向にあります。
ユーザーは資格や実績、対応分野、レビューなどの情報を比較しながら、依頼先を慎重に検討します。一部のプラットフォームでは、チャット機能や簡易相談フォームを導入しているケースもあり、初回連絡の敷居を下げる可能性がある設計とされています。
ただし、同業者も多数掲載しているため、他の専門家との差別化が不可欠です。
選ばれるためには、自身の専門性や経験、対応可能な地域を明確に伝えるとともに、顔写真や事務所の雰囲気が伝わるプロフィール設計が効果的です。
ポータルサイトは基本的に「受け身の集客メディア」ではあるものの、掲載内容を工夫することで相談につながる可能性を高めることができます。
【オフライン】士業の集客方法
オンラインが主流となった今でも、士業の特性上、オフラインの施策は依然として有効です。
ここでは代表的な4つの方法を紹介します。
【オフライン①】 セミナーの開催
士業の専門性を活かして信頼を獲得し、見込み顧客と直接つながるには、無料または低額のセミナーの開催が有効とされています。
セミナーは事務所内で行うほか、地域のカルチャーセンターや公民館など公共施設を使って実施することもできます。法律や税金といった士業分野の知識は、「必要なときに知りたい」と考えている人が多く、正確な情報を得られず不安を抱えているケースも少なくありません。
こうしたニーズに応え、専門的な内容をわかりやすく解説することで、参加者に安心感を与えられるだけでなく、口コミや紹介による情報拡散効果も期待できる可能性があります。
たとえば、相続や確定申告など、一般的に関心の高いテーマを選び、地域住民が参加しやすい日時・場所で開催することで、潜在的な顧客層にアプローチしやすくなります。さらに、自治体の広報誌や掲示板、地域のSNSグループ(例:Facebookの地域グループやLINEオープンチャット等)などを活用して告知することで、集客効果を高めることが可能です。
つまり、セミナーは専門性を可視化し、信頼構築と見込み顧客獲得の両立が期待できるオフライン施策です。
【オフライン②】 無料相談会の開催
士業への相談ハードルを下げ、気軽に相談できる機会をつくるには、無料相談会の開催が非常に効果的です。
多くの生活者が専門家に相談することをためらう背景には、「相談するとすぐに費用が発生するのでは」という不安が挙げられます。これは、商品を自由に選べる買い物とは異なり、“相談=高額な費用が発生するかもしれない”という心理的なプレッシャーがあるためと考えられます。
その点、無料相談会を定期的に実施することで、「まずは気軽に話を聞いてみよう」という雰囲気作りができ、初めての接点としてのハードルを下げる効果が期待できます。
たとえば、「毎月○日開催」「初回30分無料」などの形で継続開催すれば、地域住民に「この事務所は相談しやすい」という印象を与えやすくなります。さらに、実際に訪問することで事務所の雰囲気が伝わり、信頼感の向上にもつながるでしょう。
つまり、無料相談会は“士業との最初の接点”をつくる仕組みとして、認知拡大と相談促進の両面で効果的な施策といえます。
無料相談会の開催は、見込み顧客との関係づくりを丁寧に進めるうえでも、導入を検討したい手段の1つです。
【オフライン➂】 屋外広告の設置
地域での認知度を高めたい士業にとって、屋外広告の掲出は有効な集客施策です。
駅前や商店街、高速道路沿いのビル屋上、電車内など、人通りの多い場所に掲出することで、多くの人の目に触れる機会が増えます。繰り返し視界に入ることにより、自然と事務所名や業種が記憶に残ります。
実際に、目立つ場所に掲出された広告が話題となり、メディアで紹介されたことで問い合わせが急増したケースもあります。
このように視認性の高い広告は、士業でも“身近な専門家”という印象づけに役立ちます。
また、ホームページのURLやQRコードを広告に記載することで、詳細情報への導線を設計できます。Webページに誘導することで、問い合わせや相談申込みにつなげることも可能です。
ただし、設置場所は戦略的に選ぶ必要があります。広告費がかかるため、効果を最大化するには、事務所近隣や商圏エリアに絞って掲出することが望ましいでしょう。
遠方に掲出しても来所や相談につながる可能性が低く、費用対効果が下がるおそれがあるため注意が必要です。
屋外広告は、地域での認知獲得とオンライン誘導を兼ね備えた、オフラインとデジタルをつなぐ集客施策として活用できます。
【オフライン➃】 ポスティング
地域密着型の認知獲得や、潜在顧客へのアプローチには、チラシなどのポスティングは、今も有効な手段とされています。
ポスティングは、紙媒体による広告手法の一つであり、配布エリアを限定できる点が特長です。これにより、届けたい層に直接情報を届けられます。
特に、日常的にインターネットを使わない高齢者層などには、オンライン広告ではリーチしにくいため、補完的な施策として機能します。
また、紙のチラシは保存性が高く、必要なときに見返されやすいという利点があります。
たとえば、「相続の際に思い出してもらえる」「確定申告時期に取り出してもらえる」といったように、即時性がない場合でも記憶に残る効果が期待できます。
さらに、初回無料相談券や割引特典を添付することで、行動を促すきっかけにもなります。
つまり、ポスティングは“潜在層との接点をつくり、適切なタイミングを待つ”ための認知施策として、士業にとって堅実な集客手段と言えるでしょう。
士業で集客を成功させるためのポイント
集客施策を行う際に軽視されがちなのが、戦略的な視点(全体設計)です。
単発の施策では持続的な成果は得られません。
ここからは、士業が集客を成功に導くための5つの戦略的ポイントを解説します。
マーケティング思考を取り入れる
士業が集客で成果を上げるためには、「マーケティング思考」を取り入れることが非常に重要です。
これは「どうすれば選ばれるか」という仕組み(集客の全体設計)を作る考え方であり、単なる集客テクニックではありません。
士業はモノを売るのではなく、“悩みの解決”をサービスとして提供する存在です。相談者に「この人に頼みたい」と思ってもらえるかどうかが重要です。
そのためには、未来の顧客の生活に目を向け、「どんな場面で」「どのような不安を抱き」「どう解決したいのか」を具体的に想像することが求められます。
たとえば、「相続税の申告が不安で夜も眠れない」人に対し、「この手続きを終えると、安心して次の人生設計に進めますよ」と未来像を示すことで、選ばれるきっかけになるかもしれません。
こうした仕組みの設計は、ホームページやSNS、広告などのオンライン施策と、セミナーや相談会などのオフライン施策を組み合わせることで、見込み顧客との接点を効果的に増やせます。
つまり、マーケティング思考とは「誰に、どんな価値を、どう届けるか」を意識し、多面的に“選ばれる土台”を築く取り組みです。
顧客のニーズを深く掘り下げる
士業が信頼され、選ばれ続ける存在になるためには、顧客の「本音のニーズ(本当の要望や悩み)」を理解することが欠かせません。
多くの見込み顧客は、表面的な相談内容の裏に、不安や期待などの感情を抱えています。
顧客獲得を成功させるには、単に手続きを代行するだけでなく、「なぜその手続きを必要としているのか」「どんな結果を望んでいるのか」という根本的な理由を聞き取る姿勢が求められます。
たとえば、「相続手続きが不安」という相談の裏には、「家族に迷惑をかけたくない」「遺産を巡るトラブルを避けたい」という心理的な不安が隠れているケースもあります。
こうした背景を丁寧に聞き出すことで、士業が提供できる価値をより明確に示すことができます。
さらに、顧客の本音に向き合う過程は、自分の専門分野や強みを再確認する機会にもなります。
「自分が提供できる価値は何か」「誰のどんな課題を解決できるのか」を見直すことが、より精度の高いサービス設計につながります。
つまり、ニーズの深掘りとは、顧客理解と自己理解を同時に深める対話であり、他士業との差別化を実現する要となる行為です。
分野の専門家であることを効果的に伝える
士業が選ばれる存在になるためには、自身の専門分野と強みを明確に発信することが重要です。
競合が多いなかで信頼を得るには、「この分野ならこの人に頼みたい」と感じさせる差別化の仕組み(ブランディング戦略)が欠かせません。
たとえば、「相続に特化」「事業承継(会社の世代交代)に強い」「外国人ビザ申請に詳しい」など、具体的かつ一目で伝わる強みを示すことで、見込み顧客の関心を引きやすくなります。
一方で、自分の強みがまだ明確でない場合は、同僚や既存顧客に「どんな特徴があるように見えるか」を尋ねると、新たな発見につながることもあるかもしれません。
また、専門性をアピールする際には、「伝わる表現」にも配慮が必要です。
初回相談や説明の場では、専門用語(法律や業界特有の言葉)を避け、誰でも理解できる言葉で説明する姿勢が、信頼感と安心感を生みます。
つまり、専門知識そのものとそれをどう伝えるかの両面が、士業のブランド形成(ブランディング)を支える要素です。
自分の強みを整理し、わかりやすく発信することが、見込み顧客との信頼構築の第一歩になります。
信頼感を生み出す工夫
士業が新規顧客を獲得するためには、まず「信頼感(専門家としての誠実さや実績への信頼)」を築くことが欠かせません。
依頼を決める際の大きな要素は、知識量や実績だけでなく、「この人なら安心して任せられる」と感じさせる対応の丁寧さや誠実さです。
たとえば、専門用語(法令や税務用語など)をわかりやすく説明したり、迅速かつ誠実な対応を心がけることが、それ自体が信頼構築の基盤になります。
また、ホームページで「どんな思いで仕事に取り組んでいるのか(理念や価値観)」を明記することも、“顔の見える専門家”としての印象を強めます。
安心感を生み出す工夫
一方で、「安心感(相談しやすさ・心理的安全)」を与える工夫も重要です。
多くの人にとって、法律や税務の相談は日常的な行為ではなく、少なからず不安を感じながら専門家に相談する傾向があります。
そのため、料金体系を明確に掲載することは、費用面の不安を減らし、問い合わせの心理的ハードルを下げる効果があります。
また、実際の相談者の声や体験談(口コミ)を掲載することは、初めて相談する人に安心感を与える有効な手段です。
つまり、信頼と安心は自然に生まれるものではなく、感じてもらうための工夫と一貫した対応によって形成されます。
日々の対応や情報発信を通じて、「安心して相談できる専門家」という印象を積み重ねることが、顧客獲得につながる重要な要素の1つです。
士業事務所のWeb広告運用を検討中の方へ
近年、士業の世界でも、Webマーケティング(インターネットを活用した集客手法)の重要性が高まっています。
しかし同業他社の増加や広告出稿の常態化により、単発の施策では持続的な集客が困難になっています。
特に、「相続」「遺言」「会社設立」など潜在的なニーズが中心となる分野では、Web上に複数の導線を設け、どの媒体に、どんな情報を出すかを計画的に組み立てる必要があります。
設計された導線に基づき施策を一貫して継続すれば、限られた広告予算でも十分な成果が期待できます。
とはいえ、士業事務所がWebマーケティング専任の人材を確保するのは現実的に困難です。
SEOやリスティング広告などは専門性が高く、他業務と兼任すると十分な成果を上げにくい傾向があります。
そこで有効なのが、士業における集客事情を理解した広告代理店やWebマーケティング専門会社への外注です。
弊社(株式会社ヒューワンズウェイ)は、特定業種に限らず、Web広告とSEOを組み合わせた集客支援を提供しており、士業のクライアントにも多数の実績があります。
汎用的なWebマーケティングの知見に加え、士業特有の業務内容やユーザー心理を理解した提案が可能です。
「執務が忙しく、Web施策に時間が割けない」
「広告を出しても反応が鈍く、どう改善すればいいかわからない」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
貴事務所の強みを活かし、最適なWeb集客戦略をご提案いたします。